〈愛情深い〉
共鳴祝祭と題されたTHE BACK HORNのライブを見たあとに不意に訪れたのは、この言葉だった。
たしかに私たちは不特定多数の集合体だ。それでもこの日、数多の1が、彼らの感情の宛先としてそれぞれ確立されていたこともたしかだった。一心に愛を受け取る。そんなことが、実際に起こった。
眩しかったのは、光だけにかぎったことではない。まるで、キラキラのテープみたいに眩しく輝く愛の存在を知るに至ったのだ。実際に、ピカピカした銀色のテープが空から落ちてきた。それに等しいくらい、いや、それ以上に煌々としたきらめきのなかに、私たちはいた。
憚らずに言えば、THE BACK HORNとキラキラって、にわかには結びつかない概念である。それでもこの日は、この二つの言葉が見事に引き合ったのだった。
未公開の新曲を含め、全24曲。2時間半以上に及ぶ長大なライブは、徹頭徹尾愛が溢れる時間だった。この日生まれた情動をこれから先に連れていくためにも、心に刺さった想いの数々をここに残すことにする。
2024年3月23日。彼らの25周年を祝う大団円がとうとうやってきた。半年近く前からこの日を楽しみにしていた。何があろうと、最高にちがいない。そんな予感が心のなかを悠然と泳いでいた。
ライブハウスのときに感じるギュッと凝縮された熱量は、言うまでもなく生命力に溢れている。たしかにいついかなるときもTHE BACH HORNが放つ精彩は凄まじい。とはいえ言及せずにはいられないのは、ホールで見るTHE BACK HORNの存在感についてである。ホールで歌う彼らは、ライブハウスで見るとき以上に大きな生命体として立ち上がってくるのだ。
圧倒的な存在感を放つ彼らは陽だまりのように暖かい。あまりにもやさしいので、なんで、こんなにやさしいのだろう、と胸がいっぱいになって苦しくなる。それは一曲一曲を終えるごとに一層の切実さを帯びていく感覚だった。愛に溢れた時間とその断片を一つひとつの曲を振り返りながら書き記してみよう。
「冬のミルク」
25周年を締めくくるライブの1曲目は「冬のミルク」。四半世紀を迎えた節目に、彼らの原点に立ち返ることになった。彼らが歩んだ25年の軌跡をすべて知るわけではない。が、それでも、「冬のミルク」以上に彼らの軌跡を雄弁に語り始める楽曲はないはずだという思いを私は禁じ得なかった。
このライブが始まる前ーーーどのライブでも同じことではあるがーーー、1曲目に何が来るだろう、と私はひたすらワクワクしていた。が、蓋を開けてみればこの曲以外に選択肢はなかった。後になってみれば自明のことで、たとえそれが分かり切ったことであっても、渦中にいるときには何も分からないってことがある。まさしく、共鳴祝祭というライブの1曲目とか。
「サニー」
共鳴喝采に参加した数だけ聴くことができた「サニー」。この「サニー」という曲でTHE BACK HORNは2001年にメジャーデビューを果たした。彼らの重要な契機である曲を25周年を締めくくる日に聴くことができたのは、思っていた以上に感慨深いものがあった。
様々な節目で「サニー」を聴いているとは思うけれど、その勢いたるや。やっぱりいつ聴いても痺れるくらいにかっこいいし、「大きな手」という言葉から始まるあの歌詞のところで、おもむろに手を挙げる観客たちが織り成す一体感は狂気にして壮観である。
「その先へ」
「その先へ」を聴いたのは随分と久しぶりだ。眩しい閃光とともに描き出されるのは、彼らの始まりとこれから先の未来である。
たしかにこの日は、25周年を締めくくるという意味ではひとつの句点であり、着地点にちがいなかった。が、この日は、これから先をここから始めるための始まりでもあった。そう考えると、「始まりはいつだって ここからさ」1という歌詞がたしかな重さを伴って意識に上ってくる。
このとき、会場に向かって差し出されたマイクを思い出す。お馴染みの振る舞いを見て発露したのは、安心感と懐かしさという感情だった。ささやかな動作が、否、ささやかな動作だからこそ、たしかな愛おしさにつながるのかもしれない。
さて、これまでの3曲は彼らの〈始まり〉を代弁する楽曲たちだった。〈始まり〉を堪能した私たちは、ここからさらに様々な彼らの軌跡を目の当たりにすることになる。
「閉ざされた世界」
赤いライトが似合う。「閉ざされた世界」。「その先へ」と同様、久しぶりに聴いた曲だった。思わず「やあ、久しぶりだね」とあいさつしたくなるくらいに、随分と久しい。
記憶があまり定かではないが、「閉ざされた世界」をライブで聴いたのは5年以上前のことだと思う。仮に5年の歳月を経ていたとして、その間「閉ざされた世界」を音源で聴いたのは、おそらく20回にも満たないと思う。
それにも関わらず、この曲が思っている以上に自分自身を貫いていたことに私は唖然とした。頻繁に聴くことはなかったとしても、「閉ざされた世界」という楽曲をこれまでの人生のどこかで繰り返し聴いてきたことは、決して消えない事実として自分を貫通しているらしい。
「罠」
「罠」を初めて聴いたときは、この曲にアレンジが加えられて、まったくちがった表情を見ることが叶うなどとは夢にも思わなかった。THE BACK HORNの「罠」と言えば、うねるような旋律が特徴的で、とにもかくにも疾走感と勢いが疾風怒濤のごとく畳みかけられる歌だ。これ以上の完成度はないと思わせるくらいに、精巧に築き上げられた楽曲であることを幾度となく実感する。
だからこそ、リアレンジ版として「罠」という曲に改めて息が吹き込まれたとき、その佇まいに息を呑んだ。雄々しい楽曲が魅せる表情に恍惚としたのだ。この「罠」を聴いた瞬間、この曲がさらなる生命体に化けたと確信した。
思えば、静と動の両面から「罠」という曲を余すことなく楽しむことができるのは、このうえない贅沢である。轟き、という言葉が一等似合う「罠」。やっぱり何度聴いても痺れるくらいにかっこいい。純粋に、かっこいい。それがTHE BACK HORNが創り出す世界の一端にちがいない。
「シリウス」
このタイミングで聴く「シリウス」は感慨深さと遣る瀬無さが綯い交ぜになった一撃に等しい。個人的にこの曲には、震災を念頭に置いた曲だという印象を抱いている。だからこそ3月に聴く「シリウス」からはいつも以上に真剣なまなざしを感じる。
目の前に広がるのはライトが明滅している情景でもあるので、たしかにステージ上は物理的にも光に満ち溢れていることは間違いない。だが、ここで言いたいのはそういうことではない。
曲名のとおり、一等星さながらの煌々とした光がこの曲からは感じ取れるのだ。この目で見えるわけではない。幻覚かもしれない。それでも、青白くて力強い光が矢のように放たれるさまが、見えたような気がしたのだ。
「命は命を育て 命は命を喰らい 命は命を叫び 命は一人じゃ生かしきれない」2という歌詞が何よりも痛切な響きを伴ってどこまでもどこまでも広がっていく。痛い。
「心臓が止まるまでは」
舞台奥にあった幕が引いていく。そこにあったのはオーケストラピットではなく、大きなスクリーンだった。すかさず鳴る音楽。高らかに鳴り響く汽笛のような音。「心臓が止まるまでは」。画面に映像と歌詞が一目散に広がっていく。
正直に言うと私はその様態に既視感を覚えた。が、実際に映し出された映像を見て、これはTHE BACK HORN特有の芸術であることを悟り、忸怩たる思いとともに考えを改めた。
めくるめく切り替わっていく映像、その表面を堂々と駆け抜ける歌詞。言葉という形態を伴って歌詞が現れることによって、歌はさらなる威力を携えていった。脈管を模した文字に宿るのは、いつも以上に熱く滾る生命欲にほかならなかった。
分かり切っていたことではあるが、THE BACK HORNとその歌詞の視覚化を目の当たりにすると、それらが融合したところに生まれた才気溢れる存在感に絡めとられ、意識が飛びそうだった。
映像と歌詞が織り成す妖しい世界はまだまだ続く。
「悪人」
ちょっと具合悪くなりそう(褒めてる)、という感想を抱いた「悪人」の映像。デッサンをするときなどに使われる木製の関節人形が、もう一体の関節人形に膝蹴りを喰わらすなどのバイオレンスが繰り広げられる。映像から目が離せない。
映像と歌が相俟ったところに創出された光景に恍惚とするばかりだった。思わず映像に釘付けになる。演奏するTHE BACK HORNそっちのけで私はスクリーンを眺めてしまった。
音楽が映像によって可視化されることによって、改めてコレ自体が一つの芸術作品であることに気づく。音楽が時間の芸術であるところから、空間の芸術へと変貌する端緒がここにあったのだ。
「悪人」をライブで聴く頻度は比較的高いけれど、こんなふうに楽しめたのは今回が初めてかもしれない。馴染みのある曲を新鮮な気持ちで聴くことができる。それはつまり、好きなものをさらに好きになるということを意味している。
「コワレモノ」
COCK ROACHでもお馴染みの球根さんをひしひしと感じさせるアノ生き物たちがスクリーンに現れる。まずは全身のシルエットから。そして、一人ひとり焦点を当てられた彼らの形相が明らかになる。どれも愛嬌があってとてもよい。
登場した4体は、まぎれもなくTHE BACK HORNの4人の延長でもある。見た目に似ているとかどうとかではなくて、4人になぞらえた「愛しきコワレモノ」3として、あの生命体はスクリーンの上を蠢いていた。
これは繰り返し主張したいことだが、「神様だらけのスナック」3コールアンドレスポンスは、どんなアルコールよりもガツンとキく一撃である。
「舞姫」
「桜」、「花吹雪」、「別れ霜」、「朧月」という単語が歌詞のなかにところどころ現れていることからも明らかなように、「舞姫」は春の歌だ。
春の季語がふんだんに取り込まれているところに、とにもかくにもこの曲の奥ゆかしさを感じる。それに、桜が咲くか咲かないかのところで「舞姫」をセットリストに組み込んでくれたTHE BACK HORNは、やはりどこまでいっても情趣に富んでいる。
そこはかとなく〈和〉を彷彿とさせる音の連なりにふれると、直感的にそれが〈美〉という概念と結び付くような思いがする。そうだ、THE BACK HORNが奏でる世界は、いついかなるときも美しいのだ。分かり切っていたことを今一度噛み締める。
「舞姫」をライブで聴いたのは初めてかもしれない。「舞姫」という曲そのものが、豪華な振袖のように絢爛であることを改めて思うに至った。
「アカイヤミ」
映像と合わさったときの「アカイヤミ」の破壊力たるや。前奏と赤いライトで昇天しそうなまでに血が滾るのを感じる。このとき、私の体温は物理的に間違いなく上昇していた。
よく分からない映像はそこはかとなく不気味だった(褒めています)。変遷する映像の赤色に照らし出された観客席は蠢く赤黒い集合体となり、その場に居合わせた誰もがけたたましい音楽に身を寄せていた。
「アカイヤミ」のなかに込められた叫びに、脈打つTHE BACK HORNの命を想う。目の前で繰り広げられる狂気に、そこはかとない安心感を覚える。今、私が見ているのは、THE BACK HORNという世界一かっこいいバンドだ。たしかな興奮が血液のなかに融解していく。「アカイヤミ」の鬱屈としながらも、たしかに浄化への一途を辿る音の連なりがたまらなく爽快だった。
「アカイヤミ」が終わるとともにスクリーンに幕がかかった。この時点で、なんだか途轍もないものを見たという実感に満たされていた。
「Days」
再び、ステージ後方の幕が上がる。そこに現れたのは先ほどのスクリーンではなく、THE BACK HORNのマークを象った銀色のモチーフだった。
これまでの空気とは異なった雰囲気を肌で感じる。勢いよく飛び出す歌たちが飛び交うなかにおもむろに差し挟まれるのは、しっとりした曲たちだ。このとき、改めて深く深い呼吸ができるようになる。このゾーンはたまらなく心地よい。
バンド編成で聴く「Days」は、リアレンジ版のそれとは異なった色気と趣があって、これこそTHE BACK HORNだ!と言いたい気持ちがこみ上げてきた。
「二度とない今日という日を」4という歌詞が胸に深く突き刺さってたしかな痛みと確信に変わる。
こんなにも当たり前のことをどうして今まで忘れていたのだろう。今日という日は、もう二度とやってこない。この日のライブだって、DVDなどで映像を見ることはできたとしても、同じ様態で同じものを同じように見ることは、もう二度とできない。
そう思った瞬間に、日々生きることがどれだけ奇跡に等しいことであるか、痛感せずにはいられなかった。まるでどこかで見かける陳腐な歌詞のようなことを思ってしまったのだから、なんともきまりが悪い。
今日と同じ日は二度と体験できないことを分かったうえで、今日を憶えていよう。留められるだけ留めよう。そんなの、これまでだって嫌というほどしてきたことだ。今更合点がいって、思わず苦笑した。
一度体験したことを、そのときと同じようには味わえないからこそ、私はどうにか憶えていたいと思っていたのだろうか。そのことに気付きもしないで、それでもどうにか憶えようとしていたのはなんだかおもしろい。
私の場合、頭で考えるよりも心のほうがよっぽど理解が早い。心で感じることはいつも正しい。ものすごい速度で瞬時に理解して、それができるのだから私の心はすごい、ということにしておこう。
「あなたが待ってる」
初めて聴いたときから、あたたかくて、やさしい曲だと思っていた。でも、この日に聴いた「あなたが待ってる」は、今まで思っている以上にあたたかくて、やさしくて、眩しい歌だった。
「当たり前に見えて奇跡的に違いないこの景色を胸の中にしまっておけたなら」5
そのとき見えた景色、すなわちTHE BACK HORNが歌っている、そのひとときが、この歌詞そのものの情景だった。そうやって、胸の中にしまっておきたい景色がたくさんあるよ。そんなんばっかりだよ。
付け加えるとするならば、「あなた」と聞いて思い浮かべたい人間がいることに自分でも驚いたよ、チクショウ。
「未来」
松田晋二が一定のリズムでドラムスティックを叩くとき、「未来」が始まることを確証する。そして私は、言葉にならない言葉を叫ぶ。
振り返ると、節目のときに「未来」を聴くことが多い。10周年の武道館も、20周年の武道館も、そして、25周年の共鳴祝祭でも。
例にもれず、今回も「未来」を聴きたいと思っていたので、念願叶って心の底からうれしかった。
これまでもたびたび言及しているが、「抱きしめて恋をしたそれが全てだった」6という述懐にこそ、原初的な思いのすべてが込められていると思えてならない。
純粋さの極みは、いついかなるときも琴線に触れる。そうした妙味に折に触れて出くわすことになるから、「未来」を何度でも聴きたいと思うのかもしれない。そうした透明な気持ちに、どうしようもなく焦がれているからかもしれない。
「世界中に花束を」
ホールとか、野音とか、広い場所で聴く「世界中に花束を」は、何よりも伸び伸びとしていているから、まるで、どこまでも広がる青空のような歌として立ち上がってくる。このとき込み上げてくるのは、万感の思いというやつにほかならない。
「世界中に花束を」という曲は私にとっても大切な大切な一曲である。決定的な出来事があったわけではないけれど、なんだか、とても大切なのだ。その大切さを噛み締めるように、「世界中に花束を」という曲のなかに入っていく。
このとき私は、この曲と同じくらいに伸びやかな山田将司の声に身をゆだね、音符のなかをたゆたっていた。夢のように穏やかであたたかい時間だった。
思えば、どこへ行ったとしても帰る場所があるというのは、思っている以上に安心できることだ。THE BACK HORNが私にとって帰る場所の一つであることは、言うまでもないことだろう。「僕ら何処へ行く 何処へ行ってもまた此処に帰るだろう」7という言葉をことあるごとに思い出したい。そうすれば、きっと大丈夫だって思えるから。
「涙がこぼれたら」
鮮やかで艶がある歌だと、折に触れて思う。THE BACK HORNはいろんな歌のいろんな表情をいろんな方法で描くから、本当に目が離せない。
「刃」みたいに力強くて猛々しい歌もあれば、「理想」みたいに純粋さをギュッと凝縮した涙のように透明な歌もある一方で、「涙がこぼれたら」のように艶やかで鮮烈な歌もある。あまりの振り幅に卒倒しそうだし、見惚れるほかなすすべがない。
そしてこの「涙をこぼれたら」である。「世界中に花束を」を経て、スイッチが切り替わるようにアップテンポな曲が始まったので、有り体に言うと、ただただぶち上ってしまった。抱いている感情を突き詰めると、あまりにも簡潔で呆れてしまうよ。
「Running Away」
「Running Away」も久しぶりに聴きたいと思っていたんだ…。うれしいと口を覆ってしまう癖はマスクをしていても健在だ。
胸の底から得体のしれない熱い気持ちがこみ上げてくるのは、観客たちを煽動する演者を目の当たりにするからだろうか。そして、その姿が、想像以上に眩しいからだろうか。
折に触れて背中を押してもらってきた曲が多すぎて、その回数も、その実態も、正直に言えば定かではない。それでも、私はたしかに憶えている。彼らの歌、言葉、すべてに支えられて今日まで生きてきたことを。
「「中途半端www」じゃねぇ「途中だから、半端」今に見てろ。」8って、まさにこうした言葉を灯にしながら、時には心のなかで中指を立てていたことを思い出す。しょうもないけれど、負けないためには必要な悪態だったと、今となっては穏やかに笑える。それにしても、ここの歌詞の表現、ものすごくいいよね。
「思いがけない未来でまた笑おう」8という言葉は、たしかな約束だ。私たちの再会を心待ちにする合言葉だ。
「希望を鳴らせ」
希望の音がする。それがどんな音であるかは、THE BACK HORNのライブで聴くことができる。
「希望を鳴らせ」がリリースされたころを思い出す。すると、それが随分と昔のことであるように感じる。実際にはそんなに遠い出来事ではないのに、ここまでやってくるのにかなり長い時間がかかったような気がする。
希望という単語を耳にすると、ともすれば〈明るさ〉だとか〈期待〉などの概念が連想される。たしかに、この曲は暗くない。それでも、THE BACK HORNが歌う希望は、絶望の淵を知ったからこそ語りだせる希望が描かれていると思えてならない。
これはあまのじゃくな私の意見にすぎないけれど、表面をなぞるような耳障りのよい希望よりも、這いずった人間が語る汗にまみれた傷だらけの希望の方が、よっぽど美しくて信じてみたくなる光だと思う。
おそらく、THE BACK HORNが照らし出す希望は、そういう希望だと思う。
「コバルトブルー」
「コバルトブルー」って終盤に配置されることが多い歌だから、ある意味ではお別れの合図とも捉えられる。そんなことを、このライブが終わってから思った。終わらないでほしいな。20曲以上も歌ってもらいながら、そんなことを思ってしまうのも相変わらずだ。
「コバルトブルー」は、「もう1度始まってく」9ための歌でもあるから、お別れと同時に再会を約束する歌でもあるにちがいない。寂しいけれど、寂しいだけではないはずだ。きっと。
「太陽の花」
キラキラした歌にさらなるキラキラをってんで、破裂音とともに空から優雅に舞い落ちてきたのは銀色のテープ。「太陽の花」にピッタリすぎる演出だった。今思い出しても、笑顔で顔がいっぱいになる。
会場全体が明るくなって、笑顔も涙も全部綯い交ぜになって、楽しいも愛おしいも寂しいも全部混ざって、この日を共に過ごせたことを、心から幸せだと噛み締めるに至った。
どれだけ愛おしくても、どれだけ寂しくても、またいつか、必ず再会できるからって、この先のことは不確かなのに、確固たる期待を胸に携えながら煌めきのなかに佇む彼らを見送った。
やっぱり「太陽の花」って、何よりも煌びやかだから、華やかな終わりには相応しすぎる歌であることに100万回同意したところで本編は幕を閉じた。
「最後に残るもの」
きっとこの歌を歌ってくれるに違いないと思っていたけれど、アンコールの1曲目として改めて聴くことができたので、満ち足りた心はさらに満たされた。多幸感が満ち溢れてしまった。
出会えて良かったと思う人はたくさんいるけれど、「最後に残るもの」を聴いたときに思い浮かべる「あなた」は、THE BACK HORN以外には考えられないや。このうえない大事な宝物を世に放ってくれて本当にありがとう。
これから先、折に触れてこの有難みを噛み締め、この歌に支えられ、あたたかい気持ちになったり、涙を流したり、せわしない心の動きを経験するにちがいない。そしていつの日にか、私は自分にとっての「最後に残るもの」の正体を知ることになるだろう。
「親愛なるあなたへ」
「今日がうれしすぎて今日だけのために新曲作っちゃいました。よくある『このあと21時から解禁!』とかもないです。」と山田将司が言って、「親愛なるあなたへ」という激烈素敵な新曲をやってくれた。
このライブが楽しみすぎるあまりに、この日のために新曲を作ってしまうTHE BACK HORNの愛情深さと愛くるしさを噛み締めるとともに、彼らのことが愛おしすぎるあまり卒倒しそうになった。
印象的だったのは、「言葉を探すけれど、その言葉に救われているのは自分自身」というような歌詞だ。言葉を探すのは、自分が救われたいから。そういうことは私にも往々にしてある。何度目か分からないけれど、また惚れたよ。あと1億回聴きたい。
「泣いている人」
「あなたが幸せでありますように」10とひたすら叫んでくれる人がたしかに存在している、という事実が幸せそのもので。
それ以外に語彙はないのか!と自分をどつきたくなるが、これ以外に自分の気持ちを表す言葉もないので、私は懲りもせずに至るところでこのことばかり口にしているよ。
ともすると、こんなに幸せでいいのだろうかと、つい思ってしまう。もう、私はこのうえないくらい幸せだよ。でもきっと、明日はもっと幸せに違いない。私を貫いているのは、「どうか明日は幸せでありますように」11という祈りなのだから。
「刃」
「無限の荒野」か「刃」か、最後はどちらだろう、とワクワクする気持ちと、この曲でこのライブが終わってしまうのか、という寂しさが溶け合う心情を「刃」が切り裂いた。
この日に聴いた「刃」は、THE BACK HORNの26年目を力強く踏み出す一歩としても捉えることができる象徴的な歌だった。
というのも、「いざ往こう 信じたこの道を何処までも いざ往こう この命在る限り」12という「刃」の最後に告げられたこの言葉は、THE BACK HORNのたしかな未来を約束する信念にほかならなかったからだ。
26年目を迎えたTHE BACK HORNのこれまでの軌跡を全身で知覚した。それと同時に確信したのは、26年目の先へ、そしてそれよりもさらに先へ向かう彼らの意志だった。
THE BACK HORNがここまで音楽を続けてきてくれたことを、それから、紆余曲折と逡巡を経て各々がここまで生きてきたことを、私たちは心から祝いあった。そんな集大成がたしかにここにあった。
ライブとは文字通り生ものであり、まさに命の象りにほかならない。その場限りで鳴らされる命が、二つとして同じものはない命が、そこには息衝いている。たとえ後々映像で見ることができたとしても、あの瞬間は二度と戻らない。
刹那のなかに秘められた永遠は、一方では追憶となり、他方では忘却に収束し、昂揚と寂寞が、砂のようにザラついた感覚をたしかに残していく。それくらい、ヒリヒリとした生命活動なのだ。この時間は、THE BACK HORNのライブは。
呆れてしまうくらいに大切なものがあまりにも大切で、大好きなものがあまりにも大好きだから、その分だけ私は失うことに怯えている。せっかくなら、これで終わりと胸張って言えるくらいに、悔いがないところまで心底愛したい。まあでも、今の段階では、そんなふうに吹っ切れそうにないけれど、それも人生か。
さて、書きすぎた。改めて、THE BACK HORN25周年おめでとうございます。26年目以降もこれからも、次のライブも、THE BACK HORNを観ることができるって当たり前じゃない幸せと有難みを噛み締めながら、再会を心待ちにするとしよう。

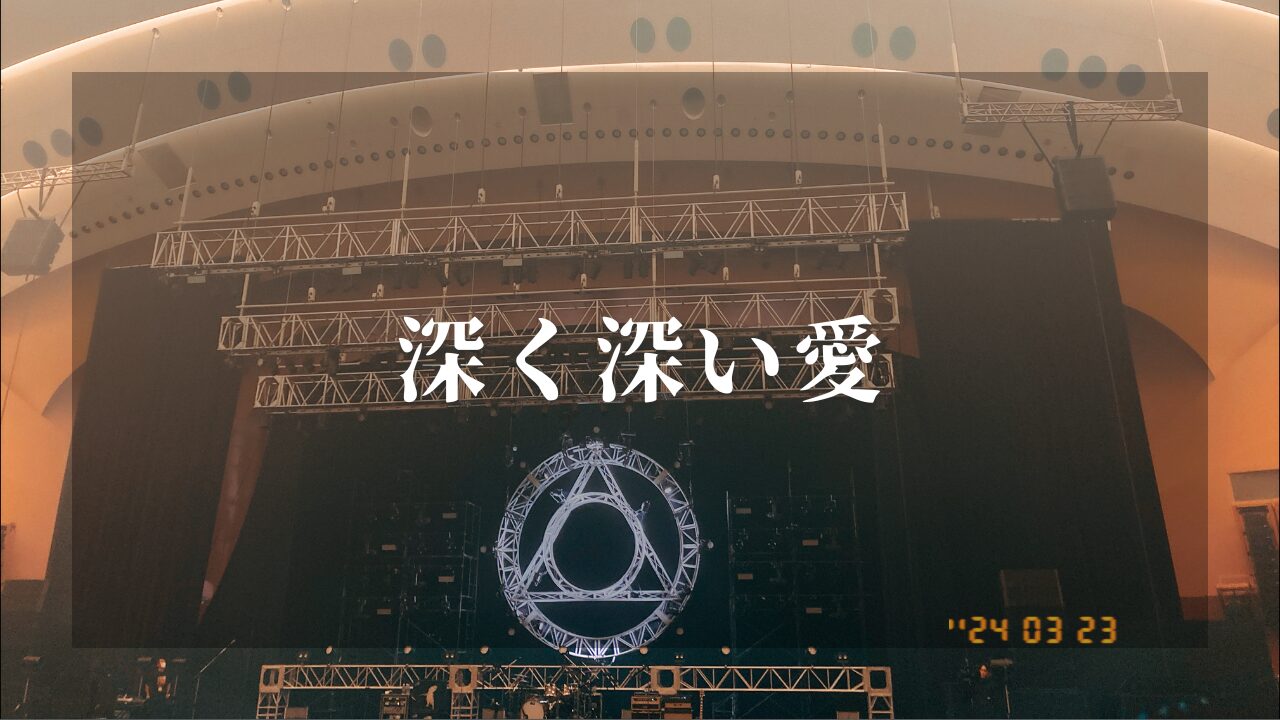


コメント