「さよならだけが人生だ」という言葉は好きだけれど、「さよならだけが人生だ」と思いたくない節がある。
こう思うに至った経緯について、10月24日に赴いたライブについてしたためながら説明してみたい。いわゆる遠征するライブというのは、目的地に吸い寄せられるようにして一点に向かっていくところがいい。会場に近づくということは、amazarashiに近づくことでもあることに胸が震えた。道中、目頭が熱くなりながら繰り返し聴いていた『七号線ロストボーイズ』。
失敗も挫折も、苦悩も後悔も、後ろめたいすべての要素に対し、今の私を構成するためにはどれも必要な部品であると捉えて肯定してくれる光がとても温かい。彼らの歌は、なぜこんなにもやさしいのだろうか。温かい光について、とりとめのないことが頭のなかをぐるぐるしていた。
ちょうど5か月ぶりに見たステージ。正直に感じたのは、あの青森での出来事を目撃してからまだ5か月しか経っていないのか、ということである。たった5か月、されど5か月。5か月あっても、相も変わらず都会の雑踏でくすぶっている私は、今回もまた途轍もないエネルギーに燃やされて真っ白になりながら言葉を探している。
言葉を表出したい気持ちだけが逸ってどうしようもない。高ぶる感情に比例するようにしてもつれる言葉。それでも書かずにいられない、拮抗するさなかでしか生まれてこない息吹があるような気がしてならない。私が表したいのはこの心である。横暴ではあるけれど、受け取った感動も、エネルギーも、すべてを言葉にして遺したい。
もう4年も前になるが、「言葉を取り戻せ」1という高らかなシュプレヒコールに扇動され、背中を押してもらい、私はようやくスタート地点に立つことができている。自分自身に嘘をつかない言葉、自分が感じたすべてをできる限り詳らかに記すこと。くどい言い方になってしまうが、そういうスタイルが私なりの言葉の取り戻し方であると今では感じている。
さて、10月24日に目撃した情景を思い出そう。ステージに登場したハットをかぶった黒い影が大きく両手を広げて指定の位置につく姿をこの目で捉えた。彼は無事だろうか、そう気にかかりながらも、伸びやかに歌う彼の姿を見て心配は安堵へ昇華された。
秋田ひろむが元気そうで、本当に本当に、とにかく本当によかった。精魂込めて歌う彼の姿を見るだけで涙が止まらなかった。轟音に掻き消された嗚咽、たぶんこれはあの場に居合わせた多くの人が安堵したことではないだろうか。
個人的には、同じセットリストを組んでいてくれたことがうれしかった。季節はめぐり冬を迎える準備をする時分、それでもこの公演は、夏を迎え撃つためのものだったと感じさせてくれた。リリースしたあとだったので「カシオピア係留所」を聴くことができるかもしれないと少し期待していた節もあったけれど、これはまた別の機会に聴けることを心待ちにしていよう。楽しみは多い方が楽しいから。
冬になるまえに聴くことができた「夏を待っていました」は、初夏の青森で目撃したライブの記憶をところどころ手繰り寄せてくれた。それがうれしかった。
美しさで鳥肌が立つことを確信させてくれた「間抜けなニムロド」。歌詞にあるとおり「どんどん速くなる」2様子は彗星のようで、なんだか無性に切なくなった。冬の冷たい空気のように凛としていて、呼吸をすると冷たい空気で肺が満たされるような気配がする。この曲は氷のように冷たく、凛然としてとても美しい。
ところでamazarashiのライブを観ていて思ったのは、自己肯定感との対峙である。amazarashiが紡ぐ歌には、その痕跡をはじめ、紆余曲折を経たからこそ言える「YES」が見て取れる。
その全てが私である。
そうやって過去の苦い記憶を肯定し、己を形成するために必要な材料だと捉える姿は、たとえば「戸山団地のレインボー」でも色濃く表されている。「失意 挫折も不可欠な色彩」3と肯定できるようになるまでに、彼はどんな苦悩を超えてきたのだろうか。推し量るだけ烏滸がましいけれど、投げかけずにはいられない疑問である。
自己肯定感という言葉は人口に膾炙するほどに高らかに語られもする。そして私も例外なく、これとどのように関わることが自分にとっての最適解なのか長らく模索しているような気がする。だからこそ感じているのは、自己肯定感というものに対し、どういう形であれ折り合いをつけられる人は幸いだということである。
たとえば自己肯定感なるものを意識せずとも自分を肯定できている人。自己肯定感という言葉に反吐が出て決裂した人。こんな自分だけど案外悪くないかもしれないと思うところから歩を進める人。自己肯定感という事象に対する関わり方は、きっと人の数だけ存在している。
自己肯定感との関わり方に対して自分なりの答えを見つけることができれば、言い換えると自分なりに折り合いがつけられたら、過度に苦しむことは減るような気がしている。かくいう私は、自己肯定感というものと未だに馴染めていないものの、拒絶しきれずに歩み寄ろうとしている諦めの悪いタイプである。
受容はいつも難い。が、自分を呪い、傷つける以外に関わり方を知らなかったころと比べれば、随分とましになったものだし、1%でも自分を肯定できるようになるとは思いもしなかったので、これはうれしい誤算でもある。
安易に「解る」という言葉をあてがえないような辛酸、他者が歩んできた軌跡について共感を示すのは烏滸がましいけれど、彼の苦悩が心に刺さって、響いて、心が震えていることはたしかである。
amazarashiの楽曲を通じて、秋田ひろむが悪戦苦闘してきた轍の一端を垣間見ながら、私は差し出がましくも自己肯定感との折り合いの付け方が見えたような気がしている。
悲しいことやつらいことは自身の軌跡のなかでもとりわけ影になりもするが、自分にとって必要な道のりだったと後になってようやく肯けることがある。過去の集積こそが今を象り、ひいては未来への水脈にもなる。
自身を否定することは容易いけれど、1%でもいいから肯定ができれば、そこから活路を見出せるにちがいない。「未来があるというのは、希望があるということ、いや希望を容れることができるということである」と言ったのは私淑する鷲田先生だ4。
とはいえ、未来へ歩を進めるということは、その分だけ死に向かい行くということでもある。「僕らはあと何回会うことができるか、あと何回笑い合えるのか」と繰り返し繰り返し語る秋田ひろむの痛切な疑問が胸に刺さる。
「生きてる限り何かの途中」5であることを銘記して己を奮い立たせもするけれど、やはり失うことだけが人生なのかもしれない、という思いは年を重ねるごとに鮮明になっていく。
この考えが腑に落ちたきっかけは「もう取り戻せないあの無邪気さ」6の存在に気付いてしまったことである。
大切な存在や身近な人が亡くなり、愛猫を含む家族は平等に老いを重ねていく。こうした翳りにあえぐのは自分も例外ではなく、これまでにない不調を抱えるなどして今までのようにはいかなくなることが増えた。そしてもう、今までのようになることはおそらく二度とないのだということも、何となく悟った。
何かを失ったとき、私たちは代替手段でそれらを埋めようと試みる。それであいた穴が保全されればそれに越したことはない。が、大抵の場合、どんな手を使ったところで埋めようがない穴の存在に痛めつけられるのではないだろうか。
たとえば〈あなた〉の存在を亡くしたとき。〈あなた〉がいなくなったことであいた穴のことを何べんも何べんも考える。考えるたびに、この穴が〈あなた〉以外ではもう二度と埋められないことを突きつけられる。なぜならば〈あなた〉は〈あなた〉以外に存在しないからである。こういうわけで、生きながらにして失うばかりの私たちは穴だらけでどうにか生きていくしかないのだろう。
とはいえ見方を変えてみれば、穴だらけのままでもどうにか生きていくことはできると言うこともできる。
「空白の車窓から」で秋田ひろむが言ったことを敷衍すれば、「取り戻せないあの無邪気さ」6の存在は、新たな展望を開くための契機である。
生きていくことの醍醐味は、取り戻せないもので穴だらけのまま通り過ぎていくさよならを知ることにもある、という希望的観測を私は捨てきれない。
もちろん、失わずにいることができるならばそれに越したことはない。しかし、喪失というものに関して、自分には必要な道のりであって、今後の糧になりうるもので、足掻きながらも己が向き合うべきこと、そして応答すべきことであると捉え直してみることはできないだろうか。
答えが出しにくいことや答えがないことというのは、たいていが自身の前に立ちふさがり、自分なりの答えが見つかるのを待ちぼうけている。この答えをどうにか見つけようと試みるけれどそれがどこにあるかは実際のところ分からない。それでもどうにか見出した答えというのは、失うばかりの人生におけるたしかな灯になるはずだという気持ちを禁じ得ない。そう思わずには、生きられそうにない。
おそらく、私が進むためにはつらい出来事とどうにか対峙する以外に道はなさそうだ。ぶつかりながら摩耗して、ようやく進むことができるのではないかと思う。だが、そこまでする理由は何だろう。そこまでしないと生きられない理由は何だろう。自分でもその説明をまだうまくできずにいる。
それでも、失ったものをもう取り戻せないという事実に挫けないこと、つまりはさよならだけの人生を受容したうえでそれに抗うことこそが私なりの応答の仕方なのかもしれない。喪失を体験しながら自分だけの言葉を見つけていくことで鷲田先生が言うところの「心の繊維」を編むことができるような気がしている。
感情というのは確かに言葉で編まれていて、言葉がなかったら、感情はすべて不定形で区別がつかない。言葉を覚えることで、じぶんがいまいったいどういう感情でいるかを知っていく。語りがきめ細やかになって、より正確なものになるためには、言葉をより繊細に使いわけていかなければならない。心の繊維としての言葉をどれだけ手に入れ、見つけていくかは、とても大事です。
鷲田清一『語りきれないこと―――危機と傷みの哲学』、角川学芸出版、2012年
失うことが人生の総体だったとして、最後の最期までこの手に残るものは何だろう。私はそれが今、無性に気になっている。だから私は「さよならだけが人生だ」という言葉を銘記しながらも「さよならだけが人生だ」ということに対して、私なりのやり方で関係しながら抗い続けたいと思う。
どうか挫けることなく、光へ、進め。
そう言った秋田ひろむの言葉はただの台詞ではなく、秋田ひろむの本心から語られた言葉である。この希いはこのうえない祝福であり、この先を照らしゆく掛け替えのない灯である。遅々として動けない自分を呪うことなかれ。この先に光はあると、かたくなに信じて、どうか、前へ進め。
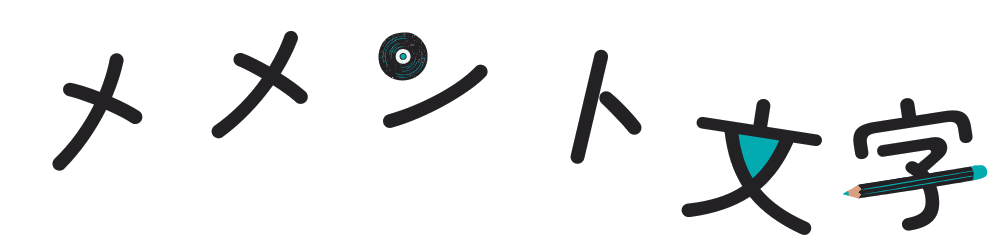
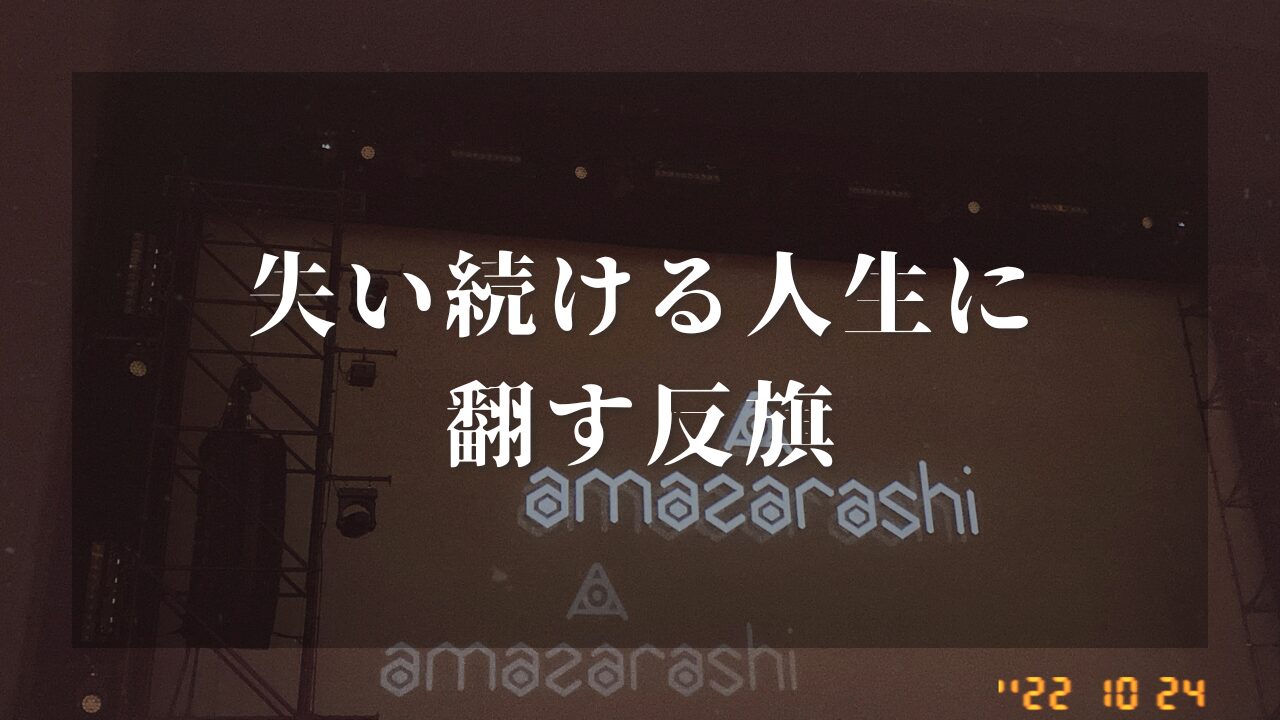


コメント