もし明日死ぬとしたら。
そんなことがふと脳裡をよぎって、されば自分はどうするだろう、と思案した。一つでも多くの感情を供養できるような墓標を建てよう。
だから未だ醒めない興奮を自分なりに咀嚼した言葉で連ねようと心が逸った。心が急くばかりで、筆は思うように進まなかったのも事実なのだが。
言葉にするために私に必要なのは、心の翳りだとか、刹那的な衝動だとか、安定しない感情みたいなもので、それが今の自分にとっては重要な燃料になっている。
だから安穏な状態では思うように言葉を紡げないし、些か剣呑な空気を帯びるからこそ拓けてくる視界があるのかもしれない。絡まった糸のように縺れた感情を完全に解けずとも、そこから何かを編みなおすことなら、もしかすると私にもできるのではないか、期待に胸を膨らませてみる。
一直線に延びた声が、歌が私の身を貫いてできた傷は今も熱を帯びて疼いている。ヒリヒリとジクジクと断続的に痛んでいる。あの場に居合わせた僥倖を一身に受けておきながら、どういうわけか痛みがやけに鮮明で、トラウマよろしく例のごとく打ちのめされている。
私が目の当たりにした二度目の青森。
初夏を目前に東北の北端は鮮やかな色を纏ってギラついていた。数か月前に出会ったモノクローム の冬から一転して、そこにはあらゆる命が呼吸をしていた。
amazarashiのライブには、これまでも幾度となく足を運んできた。そのたびに圧倒されては項垂れ、涙でぼやける視界を宝物みたいに脳内にしまい込んで、明日に向かう糧としてきた。毎回鮮烈であることには変わりない。
それでも、この日に観たすべては、私がこれまでに見てきた時間を遥かに凌駕する出来事だったと、断言せずにはいられない。披露された楽曲はもちろん、その勢いとか、それから自身を取り巻く現在の境遇だとか、それらによるすべてが引き金になって涸れない涙になった。
おそらく誰しもが、〈今、このときに聞きたい歌〉というものを胸に抱えているし、私も例外ではない。それは直感みたいなもので、内側から何かが萌芽して奏でられる脈動だ。何よりも確かな本心とでも言えるだろうか。
これは、研ぎ澄まされた嗅覚で嗅ぎ分ける本能のようなものが躍動し、一点だけを貫くような、動物的直感に近しい装置が作動することで浮上してくる核心なのかもしれない。
つつがなく過ごすことができていた日常が立ちいかなくなり、立て直すこともままならず、「当たり前」を行えなくなる恐怖と不自由さに絆された。生活が軋んださなか聞くことができた「僕が死のうと思ったのは」は、息が止まりそうなくらいに私の胸の奥を掴んで離さなかった。
「僕が死のうと思ったのは」1と徐に口を開いたときに語りだされる内容は、滔々とよどみなく話せることからは程遠いところに位置している、やっとのことでぽつりぽつりと表出される結晶なのだろう。
人の数だけ織り成される結晶に込められたもの。「僕が死のうと思ったのは」と自問自答するときに見えてくる仄暗い影。その影と和解することは一朝一夕にはいかないだろう。それでもここで強調したいのは、「僕が死のうと思った」訳を裏返せば、〈僕が生きてみようと思ったのは〉と嘯けるような、前向きな諦めなるものを見いだせる端緒にちがいない、ということだ。
「僕が死のうと思ったのは」―――だからこれは、類まれなる希望の歌なのだ。
amazarashiが灯す光は、しょうがないから明日に向かおう、とやおら思えるような、それを頼りに一歩踏み出してみようと思えるような心強い灯りだ。
どれだけ僅かな前進だとしても、0から1に向かうための原動力を与えてくれる確かな光だ。様々な局面において彼らの音楽を頼りに歩んできた私は、きっとこれからもこの灯りを拠り所に、痛みを連れ立ってどうにか前進と呼べるような一歩を踏み出していくのだろう。
痛みを伴わずして生きていくことはできないのだろうか。
そうはいっても痛手を負わない人生などは存在しえないのかもしれない。克服、と言わないまでも、和解できるくらいに、どうにか折り合いをつけられることができれば、と思わずにはいられない。
身体的なものであれ心的なものであれ、過去に受けた深い傷や痛手は、いつまでも消え去ってくれない。傷や痛手は過去のある時に受けたものであっても、なかなか過去になってくれない。それは、いくら時間を経ても、ふとしたはずみに首をもたげ、よみがえってくる。たとえば何かの情景を眼にしたとき、あるメロディにふれたとき、あるいはちょっとした湿度や気圧の変化をきっかけに。それはいつまでも過去のものとなってくれず、現在を蝕む影として、いつもいまここに居すわっている。いってみればそれは、過去になってくれない過去、人がいつまでも引きずる過去である。そして、そういう「疼き」と向き合うなかで、〈わたし〉というものが形成される。
鷲田清一『人生はいつもちぐはぐ』、角川ソフィア文庫、2016年
ちょうど同時期に読んでいた鷲田先生の言葉にふわりと掬われた。「疼き」と向き合うことで邂逅できる(あるいは形成されうる)自己があるとすれば、こうした痛みととことん話し合って折り合いをつけることができるのであれば―――。いずれにしても前途多難であるゆえ、灯りが徹頭徹尾必要である。
あの日秋田ひろむは、自身の歌を〈呪い〉だと言った。過去への復讐だとか、詳らかにしきれない悔恨だとか、そういった類を連ねた〈呪い〉なのだと。
銘々に放たれた呪いは、受け手のもとで何らかを形成し、血肉になっているはずだ。私のもとに放たれた呪いが芽吹いて発露したのは、〈それでも、生きていたい〉というような、諦めの悪さであるように思う。
生き存えたいと思う気持ちが充溢している。
本当は、生きることも死ぬことも、どちらも震えるくらいに怖いことなのに。それでも希求するのは〈生きる〉ということ。これはたしかに、ジワジワとこの身を浸食する〈呪い〉であることには変わりないのかもしれない。
たとえば若いころに、もし答えが出なければ生きてゆけないとまで思いつめていた問題が、歳を重ねるとともに色褪せて見えてくることがある。あるいは、あのときはわからなかったけれどいまだったらわかるということも起こる(……)。このように理解というものはジグザグに進んでゆく。そしてそのうち、すぱっと割り切れる論理よりも、嚙んでも嚙んでも嚙み切れない理論のほうが真実に近いといった感覚が生まれてくる。理解には、分かる、解る、判る、あるいは思い知る、納得するといったさまざまなかたちがあることも、それこそわかるようになる。
同上
今もまだ、涙を流さずにはいられないことがある。それでも、生きようと思えたのなら、恐怖を克服して、震えながらもこの足で立つことを選んだならば。
「生きてる限り何かの途中」2であるのだから。「涙は通り過ぎる駅」3なのだから。「あっち行ってこっち行って」2紆余曲折を経ながら、理解することを肚から理解していければいいだろう。受けた呪いを火種にして、「この先照らすかがり火」4とすればいいだろう。
たしかな明かりを持ちながら、夜の向こうにきっとある答えを、いつまでも、どこまでも、探し続けていけばいいだろう。

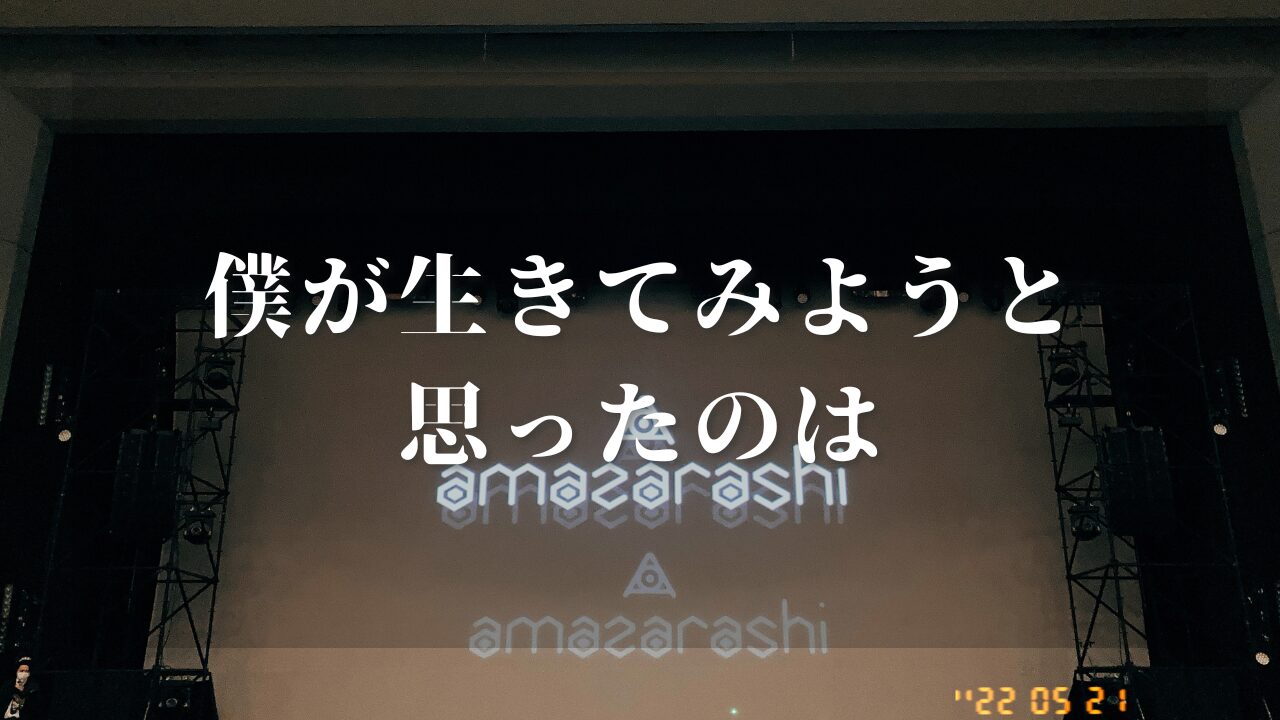


コメント