青森とは打って変わって暖かい福岡。冬はどこへ行ったのかと思わせる陽気でとても穏やかだった。中心街の雑多な印象とは対照的に、会場に向かうまで歩いた路地は思いのほか落ち着いていて、安堵の息を漏らす。ライトアップされた、灯台のように背の高い塔が見える。どうやらここは、海が近いようだ。
折よく青になった信号は、この先を迷うことなく進め、と言っているような有様だったので、私は目的地を射程に捉えながら憚らずに揚々と闊歩した。
印象的だった広々とした道、そのさきに佇む大きな建物、見知らぬ土地で行われるライブに行くと、普段以上に昂揚感に包まれる。
対極の地で見るamazarashi、なんて表現がふと思い浮かんだ。12月とは思えない陽気、冷気を孕みきらない海風、青森のそれとは全く異なる空気に泣きそうな気持ちになったのは、物理的にも精神的にも随分と遠いところまで来てしまったことによる寂寥を感じたからかもしれない。
物悲しさを感じるとすれば、雪が積もったひっそりとしたあぜ道だとか、轟々と吹きすさぶ海風に攫われる波だとか、大抵の場合はそういうものが思い起こされる。
私がここで見たものはそれらとは似ても似つかないのに、知らない街で見た夕焼けとか、冷え切っていない風とか、にぎわった街とか、自分が勝手に感じているだけのそこはかとない疎外感が、ヒリヒリ疼くような心境に至った。
青森からはもちろん、今住んでいるところからも遠い場所。空路であれば2時間程度で行くことができようとも、縁もゆかりもない街である。好きなバンド、というたった一つの光を目印にして未知の街を歩くのは、改めて考えてみると、随分と胸が熱くなる行動である。
開演前から感極まるところで再会したツアー「永遠市」は、音楽が切れるタイミングがこれまでと異なっていた。予測できない開始のタイミングを窺いながら、その時をドキドキしながら待ち構えた。
スクリーンの向こう側に、仄かな人影が見えるとたぎる。
ほかのバンドのライブだと暗転してからメンバーが登場することがほとんどだけれど、amazarashiは登場してから暗転し、即座に音が鳴るので、新鮮な感じがする。
今回のライブで改めて実感したのは、ライブに行く回数を重ねることで、自分のなかにも曲がしっかり根付いている、ということである。初めて「永遠市」のライブに参加した11月3日と比べると、たしかな手ごたえとともに、『永遠市』の楽曲たちが自分のうちに定着していることが分かる。
その間、たしかに音源を繰り返し聴いていることも事実である。が、それ以上に、まさしく百聞は一見に如かず、といったところだろうか。映像も相まって、楽曲に対する解像度が都度上がる感覚をそこはかとなく覚えた。
たとえば綴られる歌詞を心のなかで繰り返していることに気付いたとき、空で反復させることができたとき。『永遠市』の丸ごとをライブで堪能できる時間はきっと今だけだから、己の一部になりつつある過程をとても愛おしく思った。
全体をとおして印象的だったのは、秋田ひろむが、珍しく、ところどころ声が出ていなかったことである。私はこのことを決して批判したいのではなく、むしろ、これがうれしかった、ということをここでは理由を付け加えながら伝えたい。
たとえ部分的に歌詞が飛ぶことはあっても、秋田ひろむの音源を超えるまでの伸びやかで精巧な歌唱には常々圧倒される。人間離れした彼の技量には何度息を呑んでも足りない。
そこで歌っているのは秋田ひろむその人であることを言うまでもなく理解していながらも、あまりの完成度の高さには隙のなささえも感じる。
だからこそ掠れた歌声であったり、気力で絞りだされる声というのは、秋田ひろむも人間であることを改めて実感できる尊い瞬間だったのである。
たしかに彼の人間らしさは楽曲やMCなどでも垣間見ることはできようが、歌を歌う一瞬の綻びに潜んだ喜びを感じずにはいられなかった。秋田ひろむも人の子だという一面を見ることができたことが、とてもうれしかった。
だから、そういうわけで、この日のライブは普段以上に特別な体験になった。
今回のライブのMCで、秋田ひろむがおもむろに語ったのは、amazarashiとして活動することを改めて意思表明しているようにも捉えることができた。
amazarashiではやりたいことをやろうと思って全部やっている。前のバンドで失敗したから、人の言うことを聞いて、あのときこうしておけばよかったって後悔したから。
繰り返し思うのは、心底悔やむという感情の尊さである。だって、それは、心血を注ぐとか、一心不乱に取り組むことでしか沸き起こるはずのない真情の発露だからである。それらの挫折をバネにする、というだけでは到底表現しきれない彼の歩みを折に触れて知るたびに、私は、ただ胸が軋むような思いを噛み締めてばかりいる。
全部の曲が同じだとしても、一度として同じライブはない。毎回、ハッとさせられることがあって、そのたびに頭を捻って、答えを手繰り寄せようとする営みが生まれる。誕生日前夜のタイミングで、amazarashiを観ることができて、本当によかった。
さて、ようやくセットリストも馴染んできたところで、全曲とおして一言ずつ順番に感想を書いてこの日の記録としよう。
1曲目「俯きヶ丘」。宇宙は無音のはずだけど、宇宙空間を彷徨うかのようなイントロが想像力を掻き立てる。ところでエアレンデルは、地球に光が届くまでに約129億年も要する場所に位置する史上最も遠い星らしい。よく観測したよなあ、人類1。
続く「インヒューマンエンパシー」。自ら疎外感に苛まれていたマッチポンプな私のことも迎え入れてくれるやさしい歌。黎明の歌は煌めく水晶のように眩しく光る。そういえば、この歌は出航の歌だって、秋田ひろむも『永遠市』のアルバムのなかで語っていたよな。
「下を向いて歩こう」の「これが最後かもしれないから当たり前なんて思うな今が」2という歌詞が刺さって落涙。明日ものうのうと生きているにちがいない、と無意識理にインプットされているからこそ、ライブをはじめとして事あるごとに思い出したいのは、「これが最後かもしれない」ということ。
再会を心待ちにしているけれど、何があるか分からないのはお互い様だからこそ、噛み締めて味わい尽くすんだよ、私たちが今、同時に存在しているという幸福を。
何でもない日々を積み重ねるすべての人たちに、今日も歌ってくれてありがとう。「ディザスター」のなかにある「人が押し付ける褒章は 心底くそくらえ」3という歌詞には心底胸が震えるし、スクリーンに堂々と映し出される巨大な言葉の連なりも、とにもかくにも胸を突く。
「14歳」の前奏で鳴るピアノがあまりにもあたたかくて、やさしい。改めて思うのは、「今すぐ何かを始めなくちゃ」4って言って「それなら僕は歌を歌うよ」4という姿勢があまりにも眩しいってこと。今回のツアーで久しぶりに聴くことができてうれしかったなぁ。
「無題」という歌に出てくる「絵」という言葉を「歌」という言葉に置き換えれば、やむにやまれぬ衝動によって駆動し続ける秋田ひろむを思わずにはいられなかった。たとえ、この歌が、物語だったとしても。
何度聴いても圧倒される「つじつま合わせに生まれた僕等」。時計の秒針と音がぴったり重なる精巧な造りに息を呑む。文字で絵を表す映像があまりにも素晴らしくて、毎回目が離せなかった。
駆け抜けるような速度で淡々と紡がれる「スワイプ」からは、気を抜いているとあっという間に置いてけぼりにされそうな速さを感じる。映像もスワイプで変遷するような動きが仕掛けられていて、獲物を狙う猫の目よろしく言葉を追いかけた。
「君はまだ夏を知らない」のスクリーンの向こう側でやさしく揺れるテルテルは、首を吊っている。その描写とやさしい歌とのギャップがたまらなかった。「自分自身はどうか憎まないで」5だとか「自分自身にどうか失望しないで」5だとか、それらの言葉が眩しいくらいにあたたかくて、そういう願いを、自分たちの根元に据えられたらいいのにって、何度思ったことだろう。
今からでも、きっと遅くはないよな。そうした意識の欠片があれば、いつしか自分の根元に、この言葉を据えられる可能性だって、あるよな。
無理だと解っていながらも、特別な存在でありたいと願う心を無効化することはできないようだ。「月曜日」ってこんなにやさしい歌だったっけ。『月曜日の友達』を買わなくては、と思うなど。
「海洋生命」から「超新星」の流れは何度でも味わいたいカタルシスである。何度聴いても、「海洋生命」の畳みかけるようなポエトリーリーディングには毎回鳥肌が立つ。歌詞を目で追うのもせわしなく、一つひとつの言葉を捉えるには神経を集中させる必要がある。噛み砕くように聴く。全身で聴く。だから、amazarashiのライブは、座りながらにしても相当疲弊するのか。
「超新星」の映像は、はじめのうちはモノクロなのに、最後になって清冽な色味を帯びるところが何よりも眩い。まるで世界が、あるいは宇宙が色彩を帯びていくかのような情景をこの目が捉える。色数は少ないのだが、鮮やかな色彩が目の前に見事なまでに立ち現れるのだ。
「海洋生命」同様に矢継ぎ早に紡がれる言葉たちのスコールには目を瞠るものがある。呼吸をするタイミングが分からなくなるように、自身の身体にも、拳にも力が入る。息をつく間もない言葉たちが終わると同時に最後のサビを迎えた瞬間に、目の前のスクリーンは、超新星爆発を描きながら色を帯びる。ため息をつきながら、その美しさに恍惚とする。
思えば、自由に向かって逃げているのは、私も同様である。「自由に向かって逃げろ」と焚きつけられるような思いを抱えながら思うのは、私にとっての自由とは何かということ。行きたいと思ったときに行きたい場所に何の制約もなく行けることかな。今はそう思っているよ。
「空に歌えば」の速度は何よりも速い。この歌は、豪雨のあとに期待せずにはいられない青空を想起させる。「空に歌えば」には前向きな諦めが込められていて、清々しいくらいに颯爽とした歌なのに、やっぱり何度聴いても泣いてしまう。「この人生は生きるに値する」6と頑なに主張する叫びに、何度も何度も心を突き動かされるのだ。
「美しき思い出」を聴くと、自分のなかにある〈忘れていいこと〉と〈忘れちゃいけないこと〉を棲み分けるきっかけにもなっていることが分かる。それらは多くなくてもいいし、多くてもいい。
とくに〈忘れちゃいけないこと〉の指針は、自分にとっても大きな指標になるはずだ。繰り返し、銘記するんだ。〈忘れちゃいけないこと〉ってやつを。
「ごめんねオデッセイ」でところどころ声が上ずるのを聴いて図らずとも胸がはねた。絞り出すように歌う秋田ひろむを愛おしいと思うほかなかった。「海洋生命」や「超新星」同様に、連綿と続く言葉の雨に打たれるのは、このうえない浄化作用である。
「ごめんねオデッセイ」が始まる前に、「次の曲を含めて、あと2曲です。」と終わりを告げられたからこそ、終わらないでほしいと、無理な願いを心のなかで繰り返し唱えた。
「アンチノミー」が始まる前に語られる言葉たちに何度涙を落としたことだろう。完全に再現はできなかったけれど、秋田ひろむが放った言葉の一部をここに記して、この記事を閉じる。この夜のことを、繰り返し反芻するために。この夜に、いつでも想いを馳せるために。
埋め合わせようのない欠落や、永遠はないという諦めや、刹那の昂揚からふと我に返ったときに、どうしようもなく項垂れる長い夜、手持無沙汰に探るポケットのなかに、今日の音が、今日の言葉が、どうか、一欠片でも残っていますように。夜の隅っこで一人泣いていたあなたへ、どうか、どうか、生き延びて。
- https://sorae.info/astronomy/20220331-hubble-earendel.html#:~:text=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AF%E5%8F%A4%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E3%81%A7,%E3%82%82%E7%99%BA%E8%A1%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82[↩]
- 秋田ひろむ「下を向いて歩こう」、2023年[↩]
- 秋田ひろむ「ディザスター」、2023年[↩]
- 秋田ひろむ「14歳」、2011年[↩][↩]
- 秋田ひろむ「君はまだ夏を知らない」、2023年[↩][↩]
- 秋田ひろむ「空に歌えば」、2017年[↩]

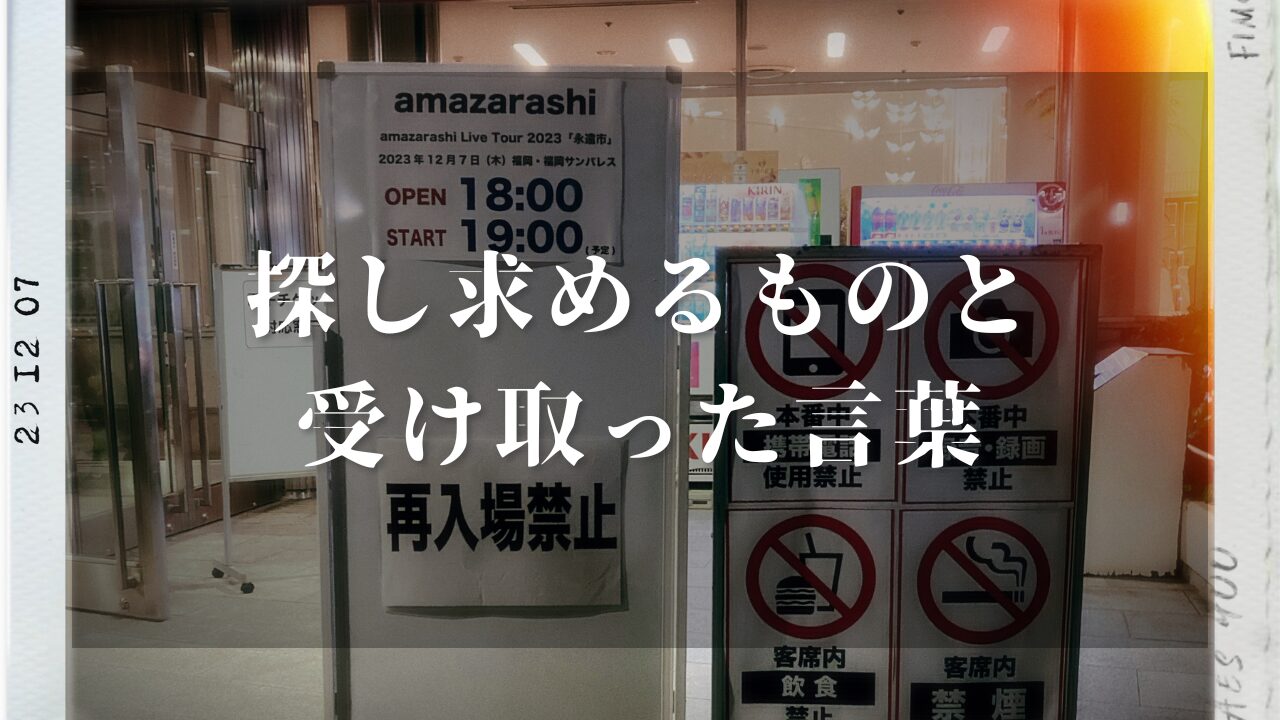


コメント