例年になく暖かい日が多いように感じる。前回の秋雨とは打って変わって晴れやかで穏やかな一日、その一日を締めくくるかのように、あと数日で満ちるであろう月の光は、渋谷の雑踏のなかでも一等眩しかった。
ポエトリーリーディングを終えて揺らめくは、「拒否オロジー」の旋律と光芒。あのたなびきのなかに自分も溶け出してしまったかのような感覚に陥っては、その美しさに涙が頬を伝う。美しさとの邂逅が涙を誘引する引き金でもあるということを、私は今回のツアーで何度となく思い知らされた。
11月16日、そういえば3年前の今日もamazarashiを目の当たりにしたのだと、ふと物思いに耽る。『独白』の衝撃を受けてから早3年。同じ日に、同じアーティストの、同じ楽曲に圧倒されるということ。
それはさながらあの日の延長線がまさしく今日につながっていたとも実感できる軌跡である。とはいえ、一方では、自分の定点が変わってしまったことを悟るにも、十分すぎる月日であることもたしかだ。
ずいぶん遠くまで来たことは紛れもない事実だが、あの日聴いた音楽があの時と変わらないまま在り続け、かつあの時と同じように感応する自分がいる、という或る種の不変によって自らの同一性に気付かされたのだった。その時私は、流れゆくもののうちに見出す輝きこそ私の核心なのだと理解したと同時に、自身の不在を悟りもした。
ここ数年過ごしてきた平坦な日々のなかで巡り合う対象には、成功も失敗も存在しない。張り合いのない生活と、そうした生活を送るばかりである自分自身を嘲りながらも、心が萎んでいく自覚だけはかろうじてあった。
いわゆる社会人になってからというもの、達成感も挫折も味わうことがないまま、ただ、何気なく毎日を繰り返している。失敗も挫折もないのだから特段傷つくことなどないのに、なぜか遣る瀬無い気持ちが涙に変わっていくのを何度も味わってきた。
意欲とも呼べる或る種の熱量が、行き場を見つけられないままずっと燻っている。もしかすると、それが自身の不在に関係しているのかもしれない。駆け出したばかりの頃は、こんなはずじゃなかった。それは明言できることだ。
同じ電車に乗り、同じ目的地へ向かっていると思っていたのに、実は並走しているだけの別々の電車に乗っていて、目的地も別々だったことに後から気付き、虚しさに苛まれることがある。
はじめのうちは紙一枚を隔てたように透けて見えさえする程度の違和感であっても、それが幾重にも重なって産まれる差は、いわば一冊の本を綴じるくらいの文字量と厚みになって、繙くにも一筋縄ではいかないのだろう。
おそらくそれは善や悪というような二項対立では捉えきることのできない事柄で、だからこそ、他でもない自分自身がそれに対して言葉をあてがうほかに、折り合いがつくことはないように思う。「言葉にならない気持ちは言葉にする」1からこそ、ようやく地平が拓けてくるからだ。
拓けた地平の先に見出すそれぞれの解、それは「言葉を取り戻」1したことによって詳らかにされる〈終わり〉の形なのかもしれない。詳らかにする過程で何とはなしに結末を悟ってしまうこともあるのだろう。
一口に〈終わり〉と言っても、和解という帰結もあれば別離という形で終幕を迎えることもあるだろう。人の数だけ存在する折り合いの数々は、必ずしも大団円と呼べるはずもなく、諦観や拒絶という形で現出することがままあるからだ。
それぞれの〈終わり〉の形、それはamazarashiがテーマにしていることの一つでもあるように思う。〈終わり〉を歌い続けること、それは言い換えると、始まりへの希求ともとれるだろう。ヒリヒリとした痛みを伴い、泣いているようにさえ見える切実な想いが、そこからは感じられるのだ。
〈終わり〉に託す希いは、きっと明日を生きるための約束なのだと思う。惜しむらくは、未来になることがなかった私の過去、あるいはいつかの過去に置き去りにした、およろ遺失物に等しい自分自身。凍結された過去たちに対して〈ざまあみろ!〉と声高々に告げ、けりをつけてあげよう。それがせめてもの餞になるはずだ。
燻り続けている熱を、私は諦めることができない。さらば、もうここにいるわけにはいかない。〈終わり〉の形はすでに見えているのだ。朝と夜をなぞるだけの平坦な日々ではあるけれど、できる限り自身の言葉を見つけていきたい。言葉を取り戻した言葉が「この先の行く末を決定づける」1ことになるのだから。
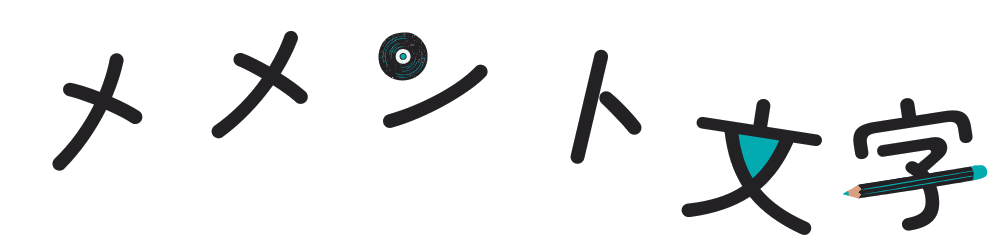



コメント