すべての曲に対して感想を書き連ねようと試みたが、どうにも収集がつかないことが分かったので、一部分だけ書き残すことにする。今回触れなかった曲はまた別の記事で。
暗転と同時に、ステージの脇から歩いてくる秋田ひろむの姿が見えた。想像していた以上に近い。私の眼は秋田ひろむをたしかに捉えたが、そのさまはタップしないと焦点がなかなか合わないスマホのカメラみたいにぎこちなかった。眼前の暗がりにポツンと立つ彼の姿を何度見ようとも、そこに現実味はなかった。
「アンチノミー」
「アンチノミー」から始まったこのライブ。その瞬間、私は先の永遠市ツアーに想いを馳せた。「アンチノミー」で幕を閉じた永遠市ツアーとは打って変わって、騒々しい無人では「アンチノミー」が口火を切ったのだ。あの日の終わりにこの日の始まりが見据えられたのだとすれば、そこからは自ずとこれから先に向かう意志が感じ取れた。まずは、今日これから始まるこのライブという未来に期待せずにはいられなかった。
「エンディングテーマ」
このライブという未来に期待したと同時に昇天しかけたのは、2曲目が「エンディングテーマ」だったからだ。「エンディングテーマ」をライブで聴くのは初めてのことだ。聴いてみたいと思っていた曲、しかもそれを弾き語り形式で聴くことが叶うなどと、誰が思ったことだろう。
初っ端からぶん殴りに来ているセトリに、武装を完全に解除した無防備な心のまま、私はなすすべもなくぶん殴られるほかなかった。今回のセトリは本気でぶん殴りに来ている。そのことをゆめゆめ覚悟をしなければならないと、私は改めて襟を正した。
「リビングデッド」
ロック少年だった秋田ひろむは、まっすぐなメッセージを放つ歌が好きで、よく聴いていたらしい。その話のなかでとくに印象的だったのは、彼がそれらのまっすぐな言葉に救われてきたことに違いはないが、心がねじれてしまったときには、どうしてもそれができなくなった、と言っていたことだ。
そんなときだったらしい。せめて自分が作る歌だけは自由であってほしい、という思いを込めて「リビングデッド」を作ったのは。
訥々と紡がれる言葉のなかに、楽曲作成の発端を知る。そういう背景を知ることはほとんどなかったので、新鮮な気持ちで「リビングデッド」を聴くことになった。
心の状態によって、好きな音楽を聴けなくなってしまうことは私にもよくある。ふとした拍子に大好きな音楽を聴けなくなる時がくるかもしれない。が、そのときには少しだけでもいいからこのことを思い出せたら、と希うばかりだ。
「ワンルーム叙事詩」
秋田ひろむによれば、当時は東京と青森との往復を繰り返しながら音楽活動を行っていて、現実感のない生活を送っていた。渋谷で初めてのライブをやったのは、そんなときだったらしい。その時渋谷の喫煙所でamazarashiのTシャツを着ているひとを見かけて、こんなところまで音楽は届くんだ、と感慨深い気持ちになったとも言っていた。
それが起爆剤になって、もっと頑張ろうと思った。そうやって作られたのが「ワンルーム叙事詩」らしい。
もっと頑張ろうという意気込みを胸に、すべてを燃やし尽くそうとした秋田ひろむの心情はどれほど熱を帯びていたことだろう。頑張ろうという決意が固くなればなるほど、彼が燃やした炎はより一層大きなものだったにちがいない。破壊衝動に彼が見据えたのは、創造にほかならない。私は、そこに息づく生命を心の底から讃えたいと思った。
「ジュブナイル」
青森市内に引っ越したばかりのころ、クーラーもない部屋で、窓を開けたまま作ったのが「ジュブナイル」だと言っていた。この歌には、当時の決意も込められていると思う、というふうに秋田ひろむは語っていた。
去年の騒々しい無人のライブの1曲目が「ジュブナイル」だったことを憶えている。「決意の歌」、「応援歌」。そんなふうに表現された「ジュブナイル」を改めて聴いたとき、この歌にこみあげられてきた底力みたいなものが突き刺さって、グッと胸をつかまれた気がした。
「令和二年」
「末法独唱 雨天決行」での配信ライブの時に、「令和二年」を弾き語りで歌ってくれたのが印象に残っている。バンド形式でこの歌を聴くのは初めてかもしれない。この曲には思っていた以上の音の厚みと奥行きがあることに驚いた。そんなふうに思ったのは、「令和二年」からバンド編成になったからというのも一つの要因かもしれない。
陽気な音調とは裏腹にこの歌が重厚な印象を与えるのは、この曲を聴くことが「令和2年」という時分に想いを馳せることにもつながっているからかもしれない。
分かり切ったことではあるけれど、音源で聴くよりも何よりも音の圧や存在感を一心に受け止めることになるのがライブである。「令和2年」という楽曲の勢いと速度、スクリーンに広がる映像に、ほんの少しだけ眩暈がしそうになった。
「パーフェクトライフ」
画面に広がる「パーフェクトライフ」の歌詞。その文字たちは、どこかしらが一部分欠けていた。そのさまは、まさしくこの歌のなかで語られるとおり、不完全なりにも完璧にちがいないことを誇らしげに表していた。
何よりも「パーフェクトライフ」を聴けたことに胸が打たれた。始まった瞬間何が起きたのか分からず、目の前に広がる光を呆然と見つめていた。「パーフェクトライフ」の映像のみならず、歌詞が連なる文字にも趣のある技巧が凝らされていることにも胸が震えた。徹頭徹尾、完璧すぎる演出だった。
「この街で生きている」
私は今住んでいる街のことをおそらくこれからも好きになることはないし、「この街で生きている」にもかかわらず、そのことを肯定することもできないだろう。しいて言えば肯定できるようになったのは、「この街で生きている」ことを肯定できない自分だ。でも、今もこれからも、それでいいと思うようになった。
終盤にかけて画面いっぱいに広がるむつ市の眺望、もっと言うと釜臥山の佇まいにグッと胸の奥をつかまれた。なぜか、涙が溢れてきてどうにも制御ができなかった。
ライブでところどころ映し出されるからこそ私も自分の目で見てみたいと思った風景、それを実際に見に赴いて、自分にとっても以前よりはなじみのあるものになった景色。そういう情景を不意に目にすると、情緒が決壊してしまう。彼らの一端を見たような気持になるからかもしれない。
「穴を掘っている」
ステージ上のすべての楽器が、それぞれに音を奏でる。それは不思議で、どこか怪しげで、ほんのすこしおどろおどろしい雰囲気を醸し出していた。聴いたことのないアレンジに、次に始まる歌への期待が高まる。「未来になれなかったあの夜に」を連想した途端、その予想はあっけなく打ち砕かれた。「穴を掘っている」。この歌をライブで聴いたことがあるのか、記憶は定かではない。おそらく初めてではないか?曲が始まる前から繰り広げられる圧巻の演奏に息を呑んだ。これだけ大きな音が掻き鳴らされているというのに、終盤に訪れる余白はあまりにも静謐としていて、特有の緊張感が漂っていた。誰もが次に鳴らされる大きな音を待ち構え、刮目していたにちがいない。ジリジリと続く静寂。あれはたしかに数秒間にわたる程度だったはずだが、それ以上に長い時間を感じさせる瞬間でもあった。
「まっさら」
永遠市ツアーではセットリストのなかに組み込まれていなかったから、ライブで「まっさら」を聴くのは今回が初めてだ。深くため息をつくようにして、心から「いい曲だなア」とこぼしたくなるような曲がamazarashiには多い。個人的には「まっさら」はまさしくそういう曲だ。
同じ曲を繰り返し繰り返し聴くことで、曲が手になじむような感覚を覚えることがある。しっくりくるような、じんわりくるような。そういう大切な瞬間をこれからも重ねたいと心から思ったし、そういう出会いのために私はライブに行くんだろうな、と確信にも似たような感覚が心のなかにあることに気づいた。
「夕立旅立ち」
秋田ひろむは、最近この曲のことが好きだと言っていた。この曲にamazarashiの未来を見た、とも言っていた。終盤にかけて加速するように、最大威力を放つようにして紡がれた「夕立旅立ち」。軽快に紡がれる音色とは対照的に、この歌はいつもどういうわけか寂寥を帯びている。「別れの歌」と題して紹介されることが多いからかもしれない。
でも、ここにamazarashiの未来を見たとすれば、この別れは寂しいだけのものではない。そんなふうに断言できるにちがいない。
今回のセットリストはとにかく凄まじいものだった。次に演奏される曲には一切見当がつかず、秋田ひろむが訥々語る言葉を頼りに、次の歌がなんであるのかを心待ちにした。間髪入れず演奏されるような迫力とはまた異なった衝撃を受けては、次の曲への期待と高揚が心地よい余白のなかを悠々と漂った。たしかにその余白は瞬間的なものにはちがいなかったが、とても愛おしい隙間だった。
そうした余白はMCにも見て取ることができた。このMCを聞いていてじんわり胸が温かくなったのは、普段のMCとの違いを実感したからだろう。これらの違いを、私はもちろん良い意味に捉えている。
いつもの整然としたMCは、楽曲たち同様に洗練された演目の一つである。それを目の当たりにするとき、手に汗を握るような緊張感が漂う。その場で語られた言葉をできるだけ聞き漏らすまいと意気込んで、言葉を繰り返し思い出したりもする。
そんなふうにして、amazarashiのライブには〈この瞬間〉のために用意された言葉たちがあちらこちらに存在している。
それとは対照的なのが、「騒々しい無人」のMCである。「騒々しい無人」では、ぽつりぽつりと紡がれる飾り気のない言葉たちに出会うことになる。そうした飾り気のなさが強調するのは、そこに秋田ひろむその人がたしかに存在している、ということだ。
これについて、少し説明を加えてみたい。
たしかに、いつのライブでも秋田ひろむの存在をありありと実感する。だが、その存在がよりはっきりと知覚されるのは、少しだけ隙間のある言葉を聞くときではないかと思う。つまりそれは、秋田ひろむが自身の心境や追懐について語っているときにふと顔を出すくだけた口調だったり、筋書き通りでなさそうな言葉選びを耳にするときである。
普段のライブのMCを〈よそいきの服を着た言葉〉とするなら、「騒々しい無人」でのMCは〈普段着を身に着けた言葉〉と表すことができそうだ。いつものライブと比べると、「騒々しい無人」で耳にする言葉にはほんの少しだけ余白がある。その言葉には、いつものライブのような精巧さはない代わりに、作り物ではないひとりの人間としての秋田ひろむという人物の輪郭が、よりはっきり感じられるように思うのだ。
なんとはなしに口を突いて出たような言葉たちに宿るぬくもりを、私は喜ばずにはいられなかった。そういう言葉も含めて、今ここでライブに立ち会っている、という実感をありありと得た。
そういうわけで、力みのない言葉を聞くことができるのも心底貴重な時間だと思うにいたった。普段のMCと「騒々しい無人」のMC、どちらが良いとかいう二元論では決してなくて、本当にどっちも好きだと心から思った。それぞれの特別を折に触れて味わうことができると思うと、どうしても口角が上がってしまう。
例によって今回のライブでも大泣きしてしまったけれど、それでも、マスク越しにほほえんでしまうような余白がところどころ自分にあったことに少し驚いた。1度目に受けた衝撃が、次はどんな情動に変換されるのか、今からとても楽しみだ。仙台公演、ありがとうございました。
- アンチノミー
- エンディングテーマ
- リビングデッド
- ロストボーイズ
- ジュブナイル
- ワンルーム叙事詩
- そういう人になりたいぜ
- 光、再考
- 令和二年
- パーフェクトライフ
- この街で生きている
- 穴を掘っている
- まっさら
- 吐きそうだ
- 夕立旅立ち
- どうなったって

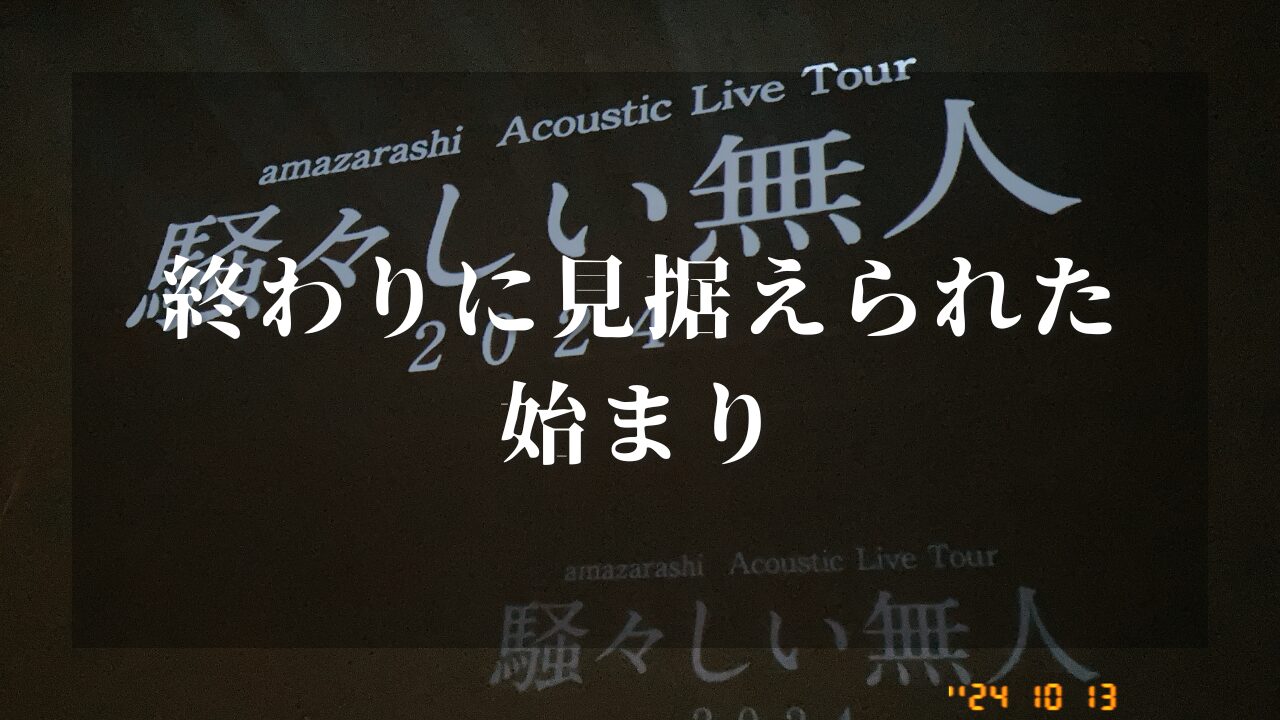


コメント